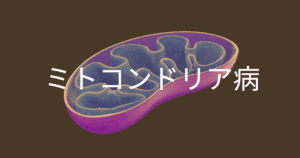脳脊髄炎・視神経炎
概要
中枢神経系症状の中で臨床的に比較的よくみられるのは、脳脊髄炎・視神経炎であり、多発性硬化症との鑑別が困難である。
Alexanderらは200人以上の原発性Sjogren症候群患者を診察
- その約20%に中枢神経系障害が存在した。
- その約1/3で多発性硬化症様の病変を伴った。
報告によって差はあるが、多発性硬化症様の中枢神経病変を伴うSjogren症候群の頻度は5-30%とされる。
臨床経過
発症様式は亜急性から慢性。再発寛解・慢性進行もあり。
視力障害・複視・顔面神経麻痺などの脳神経症状、失調や構音障害などの小脳症状、四肢麻痺・感覚障害・横断性脊髄障害など、障害部位によって多彩な症状あり。
検査
MRI:T2WI高信号病変あり。脊髄は3椎体以上の長大病変が比較的多い。
髄液検査:蛋白の軽度上昇・IgG index上昇・オリゴクローナルバンド陽性。
病理:
- 多発性硬化症では脱髄性変化がみられる。
- Sjogren症候群では神経細胞の脱落・多発性軟化壊死巣・血管壁の肥厚・脊髄くも膜下出血・前脊髄動脈のフィブリノイド壊死・血管周囲へのT細胞/MΦなどの炎症細胞浸潤などが報告されている。
- 壊死軟化の背景として小血管周囲の血管炎・血栓形成による循環障害・自己免疫機序の関与が想定されている。
治療
ステロイド治療が有効であるが、再発リスクあり。
ステロイド単剤では治療効果が期待できない場合は、IVIg・シクロホスファミドなどとの併用療法の有効性の報告あり。
無菌性髄膜炎
髄液検査:細胞数増加(初期は多核球・その後単核球優位になる)・蛋白軽度増加・IgG indexの上昇・糖は正常または軽度低下
治療:ステロイド
通常は生命予後良好。再発性であることが多い。
病理:軟髄膜へのリンパ球・形質細胞・組織球・多核白血球など多彩な細胞の浸潤あり。
自己免疫関連辺縁系脳炎
SLE・橋本脳症とならんで、Sjogren症候群もその原因疾患となりうる。
症状:難治性の痙攣発作の持続・急性発症の統合失調症様の精神症状や近時記憶障害など
MRI:T2WI・DWIで側頭葉内側に異常高信号
脳血流シンチ:側頭葉内側の血流増加
治療:ステロイド・IVIg・血漿交換
筋炎
Sjogren症候群の1/3程度にみられる。
明らかな発現機序はわかっていない。
2つ以上の膠原病が合併した場合、その症例はオーバーラップ症候群と診断されるが、Sjogren症候群と筋炎症状の合併はこのオーバーラップ症候群に位置づけられる。
多発筋炎・皮膚筋炎にSjogren症候群を合併する頻度は2.5-10%とされる。
Sjogren症候群に特異的な筋炎の臨床所見や病理組織像は知られていない。
Sjogren症候群には、明らかな臨床症状がなくても筋生検において異常所見があり、潜在的に筋炎が存在しているとの報告がある。
治療:PM/DMに準じてステロイドが選択される。
Sjogren症候群に筋力低下がみられた場合は、尿細管性アシドーシス合併による低カリウム性周期性四肢麻痺や橋本病合併による甲状腺機能低下症を鑑別疾患として考慮する。
引用・参考文献
日内会誌 99:1764-1772.2010.