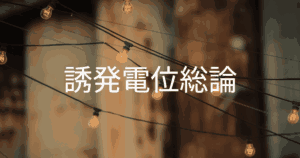概要
痛覚を生理学的または精神物理学的に定量評価する。
以下の2種類に大別される。
- static QST
- dynamic QST
static QST
概要
標準化された刺激に対する反応性をみる。
痛覚感受性のような疼痛伝達系の状態を評価する。
刺激方法:機械刺激・温度刺激・電流刺激
刺激が痛みに変わる瞬間の閾値を調べる。
圧痛閾値
広さ1cm2の圧刺激装置で、毎秒50kPaずつ圧力を上昇させて痛みを感じたところを圧痛閾値とする。
温・冷痛覚閾値
接触型のプローブを測定部位に装着し、プローブの温度を32℃に設定する。
1秒あたり1℃ずつ上昇させ、痛みを感じたところを温痛覚閾値とする。
1秒あたり1℃ずつ低下させ、痛みを感じたところを冷痛覚閾値とする。
痛覚過敏
通常でもチクチクと痛みを感じるような刺激(pinprick刺激)を与えて、痛覚過敏の有無と程度を評価する。
触覚アロディニア
通常では痛くないはずの触覚刺激を与えて、アロディニアの有無と程度を評価する。
綿棒やブラシを用いて患部をなでる。
dynamic QST
概要
疼痛の加重効果や調節機能をみる。
中枢感作や中枢性疼痛抑制系などの中枢性疼痛修飾系の機能を評価する。
時間的加重(TS:temporal summation)
圧・熱・電気などの短い侵害刺激を繰り返し与えた時に、痛覚強度が増大する現象(wind-up現象)。
侵害受容ニューロン(特に脊髄後角の二次侵害受容ニューロン)の活動電位発生頻度の増加、つまり上行性の中枢性疼痛処理過程の興奮性や中枢感作を定量化するもの。
健常者ではVAS(0-100)で10-20の増大を示すことが多い。
反応増大因子:高齢・女性・破局的思考・不安・恐怖
CPM:conditioned pain modulation
離れた部位への侵害刺激(conditioning刺激)によって、測定部(test刺激)での侵害刺激に対する痛覚強度が減弱すること。
痛みで痛みを抑制するシステムとして知られる。
広汎性侵害抑制調節(diffuse noxious inhibitory controls:DNIC)現象やheterotopic noxious conditioning stimulation:HNCSなどと表現されることもある。
下行性の中枢性疼痛抑制過程(侵害受容の下行性抑制系)の機能を定量化するもの。
健常者では痛みの尺度で29%未満の減弱を示す。
反応減少因子:高齢・女性・破局的思考・抑うつ・睡眠不足
臨床応用
慢性疼痛患者では、内因性疼痛修飾機能の障害のために、疼痛を作り出す系の過剰興奮・感作や疼痛抑制系の機能低下が生じていることが多く、TSの増大・CPMの減弱がみられる。